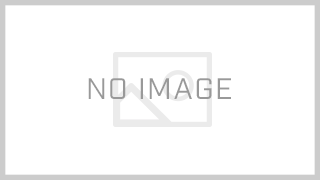この記事は、「リマーケティングって何?」「リマーケティング広告の仕組みについて知りたい」「リマーケティングの効果を上げたい」と、リマーケティング広告を配信する方の中には悩んでいる方もいるのではないでしょうか?
リマーケティングとは、広告主のウェブサイトなどを利用したことのあるユーザーに再アプローチするための広告です。
初心者向けの方への基礎知識や設定の手順などについて、また、間違いやすいポイントなどについても分かりやすく解説していくので、これから始めたい初心者の方にもおすすめです。
さっそく、ご紹介していきたいと思います。
Google広告のリマーケティングとは?

「リマーケティングリスト」とは、Webサイトに訪れたユーザーのリストのことを指します。
1度自社サイトを訪れたユーザーは、その他のユーザーに比べて確度の高いユーザーと言えます。
一般のユーザーは、サイトを訪問する際に、検索キーワードによって自分の悩みや問題、欲求を具現化しています。
実店舗に気になってお店に足を運んで考えているお客さんのイメージですが、ただ、お店に入れば物を絶対に買うかと言えば残念ながらそうではなく、その結果「高い、思っていたものと違った」、「手続きが面倒に感じた」といった様々な要因で店舗から離れてしまうことがあります。
ただ、前に1度興味をもったことには違いないので、アフターコロナにおいては「検索」と「リマーケティング」をガイドに予算を投下すべきです。
リマーケティング広告は、そのようなユーザーへCookie(クッキー)を付与し、テキストや画像、動画を用いて再アプローチをすることが出来る広告なのです。
ちなみにCookie(クッキー)とは、サイトを訪問したユーザー(ウェブブラウザ)に対して、データを一時的に保管しておく仕組みのことです。
Cookieは、ウェブサイトのログイン状態の保持やリターゲティング広告を配信する際に活用されています。
また、自社サイトへの訪問だけでなく「保存をした」「カートまで来たユーザー」「購入後一定期間を経たユーザー」という条件を設定して配信することも可能です。
Google広告のリターゲティング広告との違いは?

リマーケティング広告は、「リターゲティング広告」と呼ばれることもありますが、一体何が違うのでしょうか?
リターゲティング広告は、配信するためのコードのことで、この言い方は、Yahoo!広告で同様の配信を行なう時に使う言葉です。
リマーケティングもリターゲティングも、どちらも本質的には変わらず、管理画面から取得することができるので、特別な知識はなくても問題ないです。
強いて違いを言うなら、広告の配信先が媒体ごとに違うということくらいです。
Googleのリマーケティング広告の配信の種類について

リマーケティング広告の配信には、いくつか種類があります。
そこで、リマーケティング広告の配信の種類をご紹介していきたいと思います。
標準のリマーケティング
標準のリマーケティングとは、広告主のウェブサイトに訪問したことがあるユーザーが、ディスプレイ広告の配信ネットワーク内のサイトやアプリを閲覧しているときに広告を配信できる機能です。
リマーケティング用のタグをウェブサイトに設置して、そのタグを読み込んだユーザーをリスト化して配信対象に設定することで利用することが可能です。
メリットとしては、サイトの閲覧履歴によってセグメントを容易に作成できるのが標準のリマーケティングの大きな利点となっています。
たとえば、「商品をカートに入れたけれど離脱したユーザー」など購買意向が比較的高いユーザーへの広告配信は高い成果が得られることが多くあります。
アプリのリマーケティング
アプリのリマーケティングとは、広告主が所有しているAndroidやiOSアプリ内の行動履歴をもとにして作成したユーザーリストを使用して広告を表示するという機能です。
たとえば、ゲームアプリで一定期間アプリを起動していないユーザーへアプリの起動を促すなど、休眠顧客の呼び起こしに活用できます。
また、アプリのリマーケティングは、各広告媒体と連携可能なSDKをアプリに実装し、Google広告またはYahoo!広告に連携することで、アプリのインストールや起動回数、購入などのアクションごとにリスト化したユーザーに広告を配信することができます。
SDK(Software Development Kit)とは?
ちなみにSDK(Software Development Kit)とは、ソフトウェアを開発するために必要な技術文書やプログラムなどを一つにまとめたものです。
アプリにSDKを実装することで、アプリ内の行動履歴を測定することが可能になります。
また、各広告媒体と連携をすることが可能なSDKを実装することで、広告配信に必要な設定もできるようになります。
動的リマーケティング配信
動的リマーケティング配信とは、ユーザーが過去に閲覧した商品やサービスの情報をもとに、そのユーザーごとに最適化された広告を自動で生成・配信するGoogle広告の手法です。
通常のリマーケティングではすべてのユーザーに同じクリエイティブが表示されますが、動的リマーケティングでは「Aさんにはスニーカー」「Bさんにはバッグ」といったように、閲覧履歴に応じたパーソナライズ広告を表示できるのが最大の特長です。
この配信を行うには、まず「商品フィード」と呼ばれるデータをGoogle Merchant Centerに登録し、Google広告と連携させる必要があります。
フィードには商品名、価格、画像URL、リンク先URLなどの情報が含まれ、ユーザーの行動に応じて自動的に最適な組み合わせで広告が作成・表示されます。
動的リマーケティングは、特にECサイトや不動産、旅行、教育など、複数の商品やサービスを扱っている業種で効果を発揮しやすく、カート放棄ユーザーの再獲得にも有効です。
ユーザー一人ひとりに合わせた訴求ができるため、クリック率やコンバージョン率の向上が期待できる施策として、多くの企業が導入しています。
メールリストを活用したリマーケティング
メールリストを活用したリマーケティングとは、ユーザーのメールアドレスを使ってリマーケティング配信を行う手法です。
カスタマーマッチとも呼ばれ、広告主のもつ顧客の連絡先情報(メールアドレスや電話番号、住所など)を暗号化された状態でGoogleと共有します。
そうすることで、顧客情報に基づいたユーザーリストを作成できる機能で、リストを収集するような配信ではとても有効な手段です。
既存顧客への再度アプローチをするのはもちろん、そのユーザーリストを基に類似ユーザーリストを作成することもできます。
動画リマーケティング配信
動画リマーケティング配信とは、過去に自社のYouTubeチャンネルや動画広告を視聴したユーザー、またはチャンネル登録や高評価、コメントなどのアクションを起こしたユーザーに対して、再び動画広告を表示するリマーケティング手法です。
Google広告とYouTubeアカウントを連携させることで、こうしたユーザーの行動履歴をもとに、最適な動画広告を配信できるようになります。
たとえば、自社の製品紹介動画を途中まで視聴したユーザーに対して、その続きとなる機能説明動画やキャンペーン動画をリマーケティング広告として表示すれば、関心を持ち続けてもらいやすくなり、コンバージョンへとつなげる効果が期待できます。
また、視聴時間やアクションの有無でオーディエンスリストを分けることもでき、段階的な訴求が可能になります。
動画リマーケティングは、特に「比較検討期間が長い商材」や「ストーリーで魅力を伝えたい商品・サービス」に適しており、ユーザーとの継続的な関係づくりやブランド想起にも効果的です。
感情に訴えやすい動画ならではの表現力を活かして、ユーザーの記憶に残る広告体験を提供できるのが大きな強みです。
モバイルアプリ関連のリマーケティング配信
モバイルアプリ関連のリマーケティング配信とは、自社のスマートフォンアプリをインストールしたユーザーや、アプリ内で特定の行動を取ったユーザーに対して、再度広告を表示してアプリの再利用や再購入を促すGoogle広告の手法です。
アプリをダウンロードしただけでアクティブに使っていないユーザーや、特定の商品をカートに入れたまま離脱したユーザーに向けて、最適なタイミングで広告を配信することができます。
この手法を実現するためには、Google Analytics for Firebase や Google Ads SDK を使ってアプリ内の行動データを収集・管理し、ユーザーの行動履歴に基づいたオーディエンスリストを作成します。
そして、そのリストに対してYouTube、Google ディスプレイネットワーク(GDN)、検索連動広告などでリマーケティング配信を行います。
たとえば「アプリで商品を検索したが購入していないユーザー」には割引訴求を、「課金直前で離脱したユーザー」には特典広告を表示するなど、ユーザーの行動に合わせたアプローチが可能です。
特にゲームアプリやECアプリなど、ユーザーの継続利用が重要なジャンルにおいては、リテンションやLTV(顧客生涯価値)の向上に非常に効果的な施策です。
Googleアナリティクスのリマーケティング
Googleアナリティクスのリマーケティングとは、Googleアナリティクスで取得したユーザーデータをもとに、詳細な条件でオーディエンスリストを作成し、Google広告と連携してリマーケティング配信を行う手法です。
ユーザーのアクセス経路、ページ閲覧数、滞在時間、コンバージョン有無、デバイスや地域など、アナリティクス上で取得できるあらゆる情報を活用できるのが特徴です。
たとえば、「商品ページを3回以上閲覧したが購入していないユーザー」や「特定のキャンペーンページに訪れたが申し込みを完了していないユーザー」など、細かい行動条件を設定してオーディエンスを絞り込むことが可能です。
これにより、より関心度の高い見込み客にピンポイントで広告を表示できるため、広告の精度とコンバージョン率の向上が期待できます。
また、GoogleアナリティクスとGoogle広告をリンクすることで、オーディエンスの作成から配信までを一元管理でき、配信結果を基にした改善もスムーズに行えます。
戦略的なターゲティングが求められる中〜下層ファネルで特に効果的で、広告費の最適化にもつながる優れたリマーケティング手法です。
検索広告向けリマーケティング リスト(RLSA)
検索広告向けリマーケティングリスト(RLSA:Remarketing Lists for Search Ads)とは、過去に自社サイトを訪問したユーザーがGoogleで検索を行った際に、検索広告をカスタマイズして表示できるGoogle広告の機能です。
RLSAを活用することで、一般的な検索広告よりもターゲットを絞った配信ができ、よりコンバージョンに近いユーザーに効率的にアプローチすることが可能になります。
たとえば、一度商品ページを訪れたユーザーが再び関連するキーワードを検索した際に、より強い訴求内容の広告や特別なオファーを含んだ広告を表示するといった使い方ができます。
また、入札額を引き上げて表示順位を上げるなど、検索意図と過去の行動を組み合わせた柔軟な広告戦略がとれます。
RLSAの活用には、Google広告とGoogleアナリティクス、もしくはタグを使ってオーディエンスリストを構築する必要があります。
特に購買意欲が高い「再検索ユーザー」を見逃さず、効率よく成果につなげたい場合に有効な施策です。
コンバージョン率を高めたい検索広告施策の中でも、精度の高いリターゲティングができる手法として注目されています。
Google広告のリマーケティングのメリットとデメリット

どんなことにも「メリット」と「デメリット」が存在しています。
ここでは、リマーケティングのメリットとデメリットについてご紹介していきたいと思います。
リマーケティングのメリット
まずは、リマーケティングのメリットを見ていきましょう。
リマーケティングのメリットとしては、広告主が所有しているウェブサイトやアプリ、YouTube動画にアクセスしたユーザーの行動履歴や、顧客の連絡先情報を基にユーザーをリスト化し、そのリスト(以下、ユーザーリスト)をターゲティングした広告配信が可能になるということです。
リマーケティングを利用することで次のようなメリットを得られます。
- 購入意欲の高いユーザーに再アプローチできる
- 広告費の無駄を抑えて効率よく運用できる
- ユーザーごとに最適なメッセージが届けられる
- ブランド想起を促し、検討フェーズを後押しできる
購入意欲の高いユーザーに再アプローチできる
リマーケティングの最大の利点は、すでに自社サイトを訪問した経験のあるユーザー、つまり“購入や問い合わせに対する意欲が高い層”に絞って広告を配信できる点にあります。
こうしたユーザーはすでに商品やサービスに関心を持っているため、広告を表示するだけでもクリック率・コンバージョン率が高くなる傾向があります。
たとえば、カートに商品を入れたまま購入を完了しなかったユーザーや、料金ページを長時間見ていたユーザーに対して、特典や再訪を促すメッセージを含んだ広告を表示すれば、強力な後押しとなり、購入につながりやすくなります。
また、訪問直後だけでなく、数日〜数週間後にも広告を表示することで、ユーザーの記憶を呼び起こすリマインダーとしても機能します。
1回の訪問では行動に至らなかったとしても、継続的な接触により、ユーザーの関心を維持し続けられるので、つまり、リマーケティングは見込み顧客との関係を“切らさずに保つ”手段として非常に有効です。
広告費の無駄を抑えて効率よく運用できる
リマーケティングは、広告を表示するターゲットを「過去にサイトへ訪問したユーザー」に限定することで、より精度の高い広告運用が可能となります。
その結果、無関係なユーザーに広告を配信することによる無駄なインプレッションやクリックを防ぎ、広告費を効率的に使うことができます。
たとえば、従来のディスプレイ広告では、幅広いユーザーに対して広告が表示されるため、コンバージョンに繋がらないクリックが発生しやすく、結果としてCPA(顧客獲得単価)が高くなりがちです。
一方、リマーケティングでは、過去の接点をもとに絞り込まれた“可能性のあるユーザー”のみに配信するため、少ない予算でも高い成果を上げることが可能です。
さらに、ユーザーの行動に応じてリストを細分化し、「カート放棄者」「購入済ユーザー」「ページ閲覧のみ」などに分けて配信することで、広告費の集中投下ができ、より費用対効果の高い運用が実現します。
無駄な広告表示を減らし、本当に成果が期待できるユーザーにアプローチできるのは、リマーケティングならではの強みです。
ユーザーごとに最適なメッセージが届けられる
リマーケティングでは、ユーザーの行動履歴や属性データをもとに、パーソナライズされたメッセージを広告に組み込むことができます。
特に動的リマーケティングを活用すれば、ユーザーが閲覧した商品やカテゴリに応じて、一人ひとりに最適化された広告が自動生成されるため、訴求力の高いメッセージを届けることが可能です。
たとえば、ユーザーAには「先日ご覧いただいた商品が今だけ10%オフ」といった訴求を、ユーザーBには「残り在庫わずか!お早めに」といった異なるメッセージを自動的に表示できます。
これにより、ユーザーごとの購買意欲や検討状況に合ったアプローチが可能になり、クリック率やコンバージョン率の向上に繋がります。
また、広告の内容を柔軟に差し替えることで、リピーターには新商品を、初回訪問者には人気商品を優先的に表示するなど、一律ではなく個別最適化されたマーケティングが実現します。
ユーザーに寄り添った広告表現が可能になる点は、ブランディング強化にも繋がるメリットです。
ブランド想起を促し、検討フェーズを後押しできる
多くのユーザーは、最初の訪問ですぐに商品を購入するわけではありません。
特に高単価の商品やサービス、比較検討が必要な分野では、ユーザーが情報を集めたり、他社と比較したりする“検討フェーズ”が存在します。
リマーケティングは、この検討期間中にユーザーと継続的に接点を持ち、「忘れられない存在」としてブランドを想起させることができ、たとえば、サイトを訪れて数日経っても決断に至っていないユーザーに、何度か広告を表示することで、「このブランドは安心」「自分のニーズに合っている」といった印象を積み重ねることができます。
繰り返しの接触によって、ユーザーの検討を後押しし、最終的なアクションへとつなげることができるのです。
さらに、ブランド名や商品を目にする回数が増えることで、次に同じカテゴリの検索をしたときに「この前見たあの商品が気になる」といった“第一想起”が得られやすくなります。
検討フェーズにおける心理的ハードルを下げ、購買決定を促進するリマーケティングは、単なる追客ツールを超えてブランド構築の一環としても非常に有効です。
リマーケティングのデメリット
リマーケティングのデメリットとしては、
- 頻度が高すぎるとユーザーに不快感を与える
- ターゲットリストが少ないと十分な配信ができない
- 成果が出るまでに時間がかかる場合がある
- ユーザーの行動が限定されてしまう可能性
詳しく見ていきましょう。
頻度が高すぎるとユーザーに不快感を与える
リマーケティング広告は、ユーザーの興味・関心に基づいた再アプローチが可能ですが、広告の表示頻度が高すぎると逆効果になることがあります。
同じ広告が何度も表示されることで「しつこい」「監視されているようで不快」といったネガティブな印象を与えてしまい、ブランドイメージを損なうリスクがあります。
特に、カート放棄や資料請求のように一度明確な行動をしたユーザーに対しては、広告のインパクトが強いため、繰り返し表示されることで心理的な負担となるケースがあります。
こうした状況は「広告疲れ(広告バーナウト)」と呼ばれ、CTRやCVRの低下にもつながります。
この問題を防ぐには、フリークエンシーキャップ(広告の表示回数制限)を活用することが重要です。
ユーザー1人あたりの表示回数を1日や1週間単位で制限することで、適度な頻度で広告を届けられ、嫌悪感を抑えながらもブランドの印象を残すことができます。
リマーケティングは強力な手法ですが、「適切な頻度管理」も同時に行うことが不可欠です。
ターゲットリストが少ないと十分な配信ができない
リマーケティング広告は、サイト訪問者をベースにオーディエンスリストを作成し、そのリストに対して広告を配信します。
そのため、対象となるユーザー数が一定数以上いなければ、広告の配信が成立しない、または非常に限定的な配信になってしまうというデメリットがあります。
Google広告では、リマーケティングリストに最低100人以上(ディスプレイ配信の場合)が必要とされています。
特に、立ち上げ直後のWebサイトやニッチなサービスを扱っている場合、訪問者数自体が少ないため、リストの規模が不足し、広告を出したくても配信できないという事態が起こりやすくなります。
また、セグメントを細かく分けすぎても、各リストが分散しすぎて表示機会が減ってしまう恐れもあります。
この問題を解消するには、まずは一定のアクセス数を確保するための集客施策(検索広告・SNS広告など)を同時に行うことが重要で、そのうえで、リストのサイズに応じて柔軟に配信戦略を調整し、段階的にリマーケティングの精度を高めていくことが求められます。
成果が出るまでに時間がかかる場合がある
リマーケティングは、正確なオーディエンスデータに基づいた広告配信が可能な一方で、成果が出るまでに一定の準備期間や調整時間を要するという特徴があります。
まず、広告配信の前提として訪問ユーザーの情報を蓄積する必要があるため、新規サイトやアクセス数が少ない状態では、十分なターゲットリストが構築されるまでに時間がかかります。
また、広告運用開始後も、オーディエンスの行動や反応を見ながら広告文やクリエイティブ、表示頻度などを調整していく必要があり、最適な配信にたどり着くにはPDCAの繰り返しが欠かせません。
特に、業種によっては購入までの検討期間が長いため、短期的なCVを期待すると「思ったより効果が出ない」と感じてしまうこともあるでしょう。
このような特性を踏まえると、リマーケティングは“すぐに成果が出る即効性のある手法”というよりも、中長期的に信頼関係を築いていくリード育成型の施策として考えるのが適切です。
即効性を求める場合は、他の広告施策と並行して取り入れ、じっくりと育てる視点が必要になります。
ユーザーの行動が限定されてしまう可能性
リマーケティングは「過去に何らかのアクションを取ったユーザー」に絞って広告を配信するため、ユーザーの過去の行動パターンに依存しすぎてしまうという側面があります。
これは裏を返せば、新たなニーズや未発掘の顧客層にリーチできないということでもあり、広告の視野が狭くなるリスクがあります。
たとえば、「特定のページを見た人」だけに広告を配信していると、サイトを訪れていない潜在顧客や、別の切り口からアプローチすべきユーザーを取りこぼす可能性が高まります。
結果的に、新規ユーザーの獲得チャネルが弱くなり、成長のチャンスを逃してしまうこともあるのです。
さらに、ユーザーの行動は日々変化し、過去に興味を示していた商品に対する関心がすでに薄れている場合でも、リストに残っている限り広告が表示され続けてしまうこともあります。
これでは逆効果になることもあるため、過去のデータに固執せず、常にリストの更新や対象範囲の見直しを行う運用が求められます。
リマーケティングの効果を最大限に発揮するには、他の広告施策と併用し、バランスの取れた配信戦略を設計することが重要です。
Google広告のリマーケティングの設定方法

リマーケティング広告の配信を行なうためには、もちろん設定が必要です。
リマーケティング広告は、リマーケティングタグ(サイトリターゲティングタグ)を取得する必要があります。
タグの設置を行うことで、ユーザーデータ「Cookie」を取得しリマーケティング配信に利用できるようになります。
Cookieとは、Webサイト上でのユーザーを識別する機能で、ECサイトで1度入力した情報が自動的に表示される仕組みです。
リマーケティング機能が利用できるサービスはいくつかありますが、ここではよく使われる2媒体をご紹介したいと思います。
①Google広告でキャンペーン設定を選択する
まず、Google広告にログインして「キャンペーン設定」を選択します。
キャンペーンタイプには「ディスプレイネットワークキャンペーン」と「検索ネットワークキャンペーン」がありますが、この時「ディスプレイネットワークキャンペーン」を選択して、キャンペーンを作成します。
「検索とディスプレイキャンペーン」を選択してしまうと、検索枠にまで表記されて意図しない配信を行う可能性があります。
②リマーケティングタグを取得する
次に、Google広告から「リマーケティングタグ」を取得します。
そして、共有ライブラリのユーザーリストから、広告を表示させるユーザーの条件を設定します。
ここで「新しいタグ」をクリックすると、リマーケティングタグが発行されます。
初歩的なことですが、グローバルサイトタグがすべてのページに設置できているか確認する必要があります。
タグを設置するページの例としては、
- TOPページ
- 商品一覧ページ
- 商品詳細ページ
- 申込内容入力ページ
- 申込内容確認ページ
- サンクスページ
タグは、漏れがないように設置するようにしてください。
タグ設置の確認が完了したら、今後はタグが有効か確認する必要があります。
[ツールと設定] から[共有ライブラリ]から[オーディエンスマネージャー]をクリックします。
[オーディエンスソース] からGoogle広告タグの[詳細]をクリックすると、グローバルサイトタグのステータスのメニューが表示されます。
[オーディエンスソースは、過去24時間アクティブです]と表示されていれば問題ありませんが、アラートが出ている場合は、設置ミスの可能性があるので、正しく設置されているか(コピペ、設置箇所など)をご確認ください。
③有効期間ごとに入札単価を変える
「有効期間(=リーセンシー)」とは、ウェブサイトに流入したユーザーをオーディエンスに登録しておく日数のことです。
リーセンシーの期間が短いほどCVRが高く、期間が短くなるにつれてCVRは低下していきます。
運用事例として、全国に店舗がある弊社クライアントのリーセンシー別の実績です。
リーセンシーの期間を1日・7日・30日で複数リストを作成して配信した結果、「1日」が最もCVRが高くなることが分かりました。
| リーセンシー | 表示回数 | CVR | クリック単価 |
|---|---|---|---|
| 01日 | 1,041,806 | 1.50% | 134 |
| 07日 | 1,802,089 | 1.12% | 118 |
| 30日 | 2,840,061 | 0.95% | 110 |
例えば、以下のように入札する単価を調整比率を調整することで効果的に配信できます。
- 01日:入札単価+20%
- 07日:入札単価+10%
- 30日:入札単価+0%
ページの深い階層まで見てくれているユーザーほど、自社の商品やサービスに高い興味を持ってくれているので入札を強化すると効果的です。
④タグをWebサイトやアプリに挿入する
取得したリマーケティングタグを、Webサイトやアプリに挿入していきます。
モバイルアプリのセクション全体や、Webサイトのそれぞれのページなどにリマーケティングタグを貼り付けてください。
ここで、タグマネージャーと呼ばれる「タグ」の一括管理ツールを使うととても便利です。
⑤リマーケティングリストを作成する
最後に、Webサイトを閲覧したユーザーのリマーケティングリストを作成します。
リマーケティングリストを使いこなす事で、上記で説明した「コンバージョンをしたユーザー」や「カート落ちユーザー」への配信をしたり、また、配信除外もすることが可能になります。
ここまでの手順を踏まえて、ユーザーの画面にリマーケティング広告を表示させることができます。
作成を行ったリストはしっかりキャンペーン(実質広告グループへ)紐付けするようにしましょう。
Google広告のリマーケティングの配信戦術

リマーケティングをする際は、ただ設定をして広告を配信して終わりではありません。
配信してからが重要で、どのようにユーザーリストを設計し、どのように運用コントロールを行うかというしっかりとした戦術が必要となってきます。
その方法はさまざまで、広告主のウェブサイトが複数ドメインある場合に活用したり、訪問者の購入モチベーションを加味したり、ロイヤリティの高い訪問者へのアプローチなど、たくさんあります。
せっかく配信したので売り上げを伸ばしたいですよね。
ここからは、売り上げを伸ばすための配信戦術をご紹介したいと思います。
異なるドメインへ訪問するユーザーへの配信
異なるドメインへ訪問するユーザーへの配信ということです。
リマーケティングは、異なるドメインに訪問したユーザーに対しても、広告を配信することが可能となっています。
たとえば、広告主が保持しているメディアサイト(例:http://A.jp/)などにリマーケティング用のタグを貼り付けて、そのメディアサイトに訪問したユーザーに広告主のサービスサイト(例:http://B.jp/)の広告を配信する、などといったことが出来ます。
追跡期間に応じた段階的な配信を検討
次に、追跡期間に応じた段階的な配信を検討するということです。
リマーケティングは、ユーザーのモチベーション毎にそれに合った配信をして、さらに強弱をつけることで、より成果を上げることに繋がります。
たとえば、Googleアナリティクスでコンバージョン>マルチチャネル>所要期間(Google アナリティクスでeコマースの設定をしている場合は、コンバージョン>eコマース>購入までの間隔)を見て追跡期間ごとにリストを分けることが出来ます。
そこで、それぞれの段階に応じた入札を行うというやり方があります。
デメリットとしては、細分化しすぎると十分な広告配信ができなくなったり、データが細切れとなって最適化や分析が行いづらくなります。
なので、どの程度までリストを細分化するかは、リストのボリュームと相談して検討することをおすすめします。
また、スマート自動入札を利用する際にも、ユーザーがそのリストに登録されてからの経過時間も考慮されるので、必要以上に期間を区切るのは避ける方がいいと思います。
購入者への配信
最後は、購入者への配信です。
リマーケティングは、プロダクト提供当初は原則的に、未購入者への初回購入を促すための代表的な施策の1つとしてありました。
しかし、今では当初と変わってリマーケティングを顧客に向けて配信することで多くのアプローチをすることを可能にしています。
たとえば、過去に商品を購入したことのあるユーザーに広告を配信して商品の再購入を促したり、Gmail広告のリマーケティング配信でメルマガの役割を補完することもできます。
Google広告で質の高いユーザーリストの作り方とは?

リマーケティングの効果を発揮するにの大事なのは「ユーザーリスト」に蓄積されたユーザーの質にあります。
たとえば、1,000人蓄積されたユーザーリストがある場合、コンバージョンに近い100人が含まれたユーザーリストと、コンバージョンに近いユーザーが10人しか含まれていないユーザーリストだったら、断然前者の方が効果的です。
ここで、質の高いユーザーリストを作るためには何をどうしたらいいのか?ということです。
たとえば、トップページだけに訪問をして、商品やサービスの詳細を見ずに離脱した人は、その後購入には繋がりにくいと考えられます。
また、マイページのログイン画面まで到達したユーザーは、リターゲティング広告を配信しなくても継続購入する可能性があるので、新規ユーザーの獲得施策などの既存ユーザーを対象外としたい場合は除外してもいいと思います。
さらに、他にも年齢や性別、地域なども同様に除外を検討する材料となります。
このようにターゲット以外のユーザーの除外ユーザーリストを作成して除外することで、より質の高いユーザーリストを作成できます。
ユーザーリスト作成時の注意点

ユーザーリストを作成する際には、意図しないユーザーリストが生成されかねません。
なので、ここでユーザーリストを作成する際の注意点をご紹介します。
URL指定時に「http://」と「https://」は含めない
まず、注意点としては、URL指定時に「http://」と「https://」は含めないということです。
「http://advate.co.jp/blog/」と指定してしまうと、「https://advate.co.jp/blog/」を訪問したユーザーは含まれなくなってしまいます。
なので、あえて「http://」と「https://」を分けたい場合でない限りは、これらをURL指定時には含めないようにしましょう。
過去の訪問者を含めるか含めないか
Google広告のリマーケティングは、「過去30日間にルールに一致したユーザーをリストに事前入力する」ことで、指定したルールに応じて蓄積された訪問者を含めた状態でユーザーリストを作成できます。
また、新規にリマーケティングをはじめる場合は、リマーケティング用のタグを設置してから広告配信の開始までの期間のデータが蓄積されているので、新たなデータ蓄積を待たずに広告配信を行える状態になれる場合があります。
しかし、なんらかの影響によってユーザーリストの質が悪くなった場合については、変わってきます。
ユーザーリストの質が悪くなった場合は、「ユーザーを含まない状態で開始する」を設定して、ユーザーリスト作成後にユーザー蓄積を行います。
また、新たに同条件でリフレッシュしたユーザーリストを作成したい場合などについても設定方法は同様です。
質のいいユーザーリストを作成するために、必要なものとそうでないものをしっかりと区別するようにしましょう。
Google広告のリマーケティングの設定と運用のコツ!基礎知識から効果を高める方法!まとめ

今回は、Google広告のリマーケティングの設定と運用のコツと基礎知識から効果を高める方法を解説してきました。
リマーケティングは、ユーザーリストの質に左右されるといっても過言ではありません。
なので、まずは質のいいユーザーリストを作成して導入することに重要視するようにしましょう。
サイト訪問者へ再度アプローチするための広告というだけではなく、訪問者のモチベーション、訪問者の意向と商品サービスのマッチングなど、とても奥が深い広告です。
注意してほしいのが、ユーザーリストを特定して細かく分けすぎてしまうことです。
ユーザーリストを細かく分けることで、誰に何を配信しているかがわからない、そもそも配信に必要なユーザー数がユーザーリストの分散によって確保できないなどの弊害が発生してしまいます。
また、度がすぎると「追跡期間が長い」、「いつも同じ会員登録を迫られる」など、お客様に不快感を与えてしまう事態も避けるようにしましょう。
基本となる仕組みとルールなど概要をしっかり理解して、そして節度を守った使い方でリマーケティング配信をしていきましょう。
また、目的をあった組み合わせをすることによって、ビジネスの幅を広げて向上させていきましょう。
講座ビジネス・コンテンツビジネスの広告運用で成果に伸び悩んでいませんか? ・売り上げが伸びない と運用にお困りの方、セカンドオピニオンとして、まずはアドベートにご相談ください! アドベートは176社の運用実績があり、弊社独自のノウハウで、億超えのスクールを10社以上生み出しています。
サポートしている業種も様々で、 ・起業塾 等々。 実績としましては、 ■経営コンサルタント After ■整体手技講座 After という圧倒的な結果をたたき出しています。 弊社では、運用の成果を最大限に発揮するために下記に当てはまるお客様の支援をしたいと思っております。 ・商品、サービスに自信があり、本当に良いものをお客様に届けたいという会社様 ・担当コンサルタントを対等なビジネスパートナーだと考え、互いに配慮したコミュニケーションを望む会社様 ・同じ目標達成のために、積極的に両社協力して進められる会社様 ご賛同いただけましたら、下記ボタンをクリックして詳細を確認してください。 |